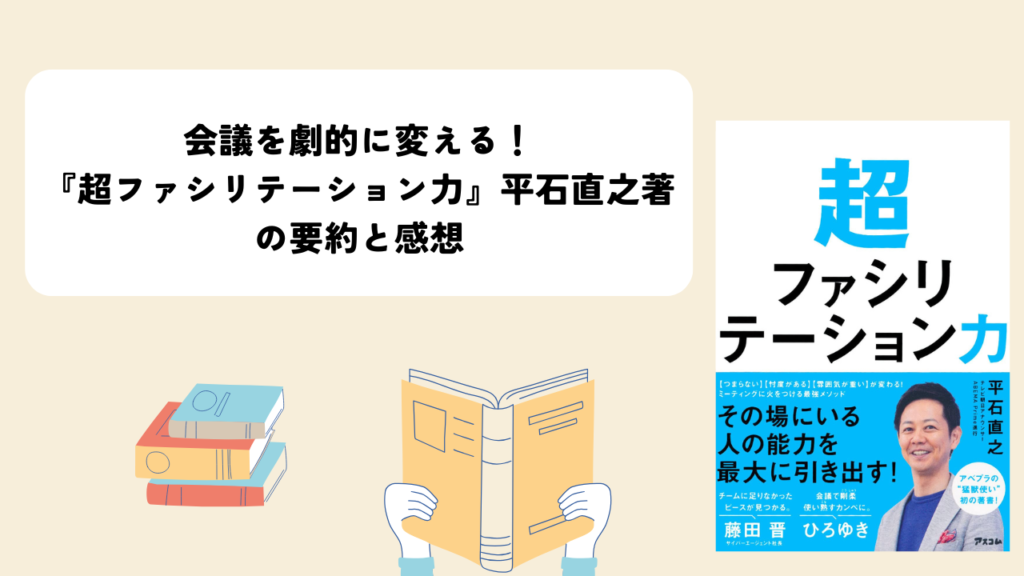
会議が長引くだけで結論が出ない、意見が出ずに沈黙が続く──そんな課題を抱えている職場も多いのではないでしょうか。平石直之著『超ファシリテーション力』は、会議を成果につなげるためのファシリテーションスキルを体系的に学べる一冊です。キャリアコンサルタントとして、チームでの円滑な議論や意思決定を支援する場面が多い私にとって、本書は非常に有益な内容でした。ファシリテーション力を高めたい方にぜひおすすめしたいポイントをまとめます。
本書の要約
1. ファシリテーターの役割とは何か
平石は、ファシリテーターの最も重要な役割は、会議の場を適切にデザインし、議論をスムーズに進めることだと述べています。単なる進行役ではなく、参加者が意見を出しやすい雰囲気を作り、議論を具体的な成果に結びつける責任を持っています。特に、「会議の目的を明確化する」「参加者の関与を引き出す」「結論を具体化する」の3つがファシリテーターの基本的な役割として挙げられています。
2. 会議をデザインする技術
平石は、会議を成功させるためには、事前準備が重要だと強調しています。以下のポイントが紹介されています:
- 目的の明確化:会議のゴールが「情報共有」なのか「意思決定」なのかを明確にする。
- アジェンダの設計:時間配分を考慮しながら、各議題を整理する。
- 適切なメンバー選定:議題に関与する必要なメンバーを揃える。
これにより、無駄のない効率的な会議運営が可能になります。
3. 意見を引き出すためのテクニック
議論を活性化するために、ファシリテーターが取るべき具体的な行動として、以下が挙げられています:
- 「聞く力」を発揮する:参加者の発言を遮らず、傾聴の姿勢を見せる。
- 沈黙を恐れない:発言が止まった場合でも、すぐに次の話題に移るのではなく、時間を取ることで新たな意見が生まれる。
- 質問力を活用する:「具体的には?」「それはどのような意味ですか?」といった質問で議論を深める。
特に、参加者の中で発言が少ない人にも声をかけ、全員が議論に参加できる環境を作ることが重要です。
4. 議論の停滞を防ぐ工夫
議論が白熱しすぎて本題から逸れる、あるいは全体が迷走する場合には、以下のようなテクニックが効果的です:
- メタファシリテーション:議論が行き詰まった際に、「今の話は議題とどう関係していますか?」など、全体の方向性を振り返る質問を投げかける。
- タイムキーパーの役割:時間配分を守り、議論を効率的に進める。
- グラフィックレコーディング:ホワイトボードやフリップチャートを使い、議論の内容を可視化することで、全員が同じ方向を向けるようにする。
5. 具体的な結論を導く方法
平石は、会議の成果は「具体的なアクションプランに落とし込むこと」だと述べています。議論のまとめ方として、以下が挙げられています:
- 「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確化する:曖昧な結論ではなく、具体的なタスクを設定する。
- 合意形成を確認する:参加者全員が納得した状態で会議を終えることで、行動につながる。
感想
『超ファシリテーション力』は、会議を効率化し、成果を上げるための具体的なスキルと考え方が詰まった一冊でした。特に印象的だったのは、「ファシリテーターは単なる進行役ではなく、場のデザインと議論の成果を導く責任者である」という点です。この考え方を取り入れることで、会議そのものの価値が大きく変わると感じました。
また、私自身、クライアントと目標設定を行う際に、アジェンダの設計や質問の仕方が非常に重要であることを実感しています。本書のテクニックを活用することで、より効率的で生産的なコミュニケーションができるようになると感じました。
さらに、「沈黙を恐れない」というアドバイスは、多くの人が見落としがちなポイントだと感じます。沈黙の中で生まれるアイデアや意見に注目し、参加者が深く考える時間を意図的に設けることで、会議の質が格段に向上します。
まとめ
『超ファシリテーション力』は、会議を成果に導くための具体的なスキルと実践例が満載の一冊です。議論を活性化し、全員が参加する場を作るための工夫や、最終的な結論を具体化する方法が学べます。キャリアコンサルタントとしても、本書のスキルを活かしてクライアントとの話し合いをより生産的なものにしたいと感じました。会議や議論を改善したい全ての人におすすめの一冊です。
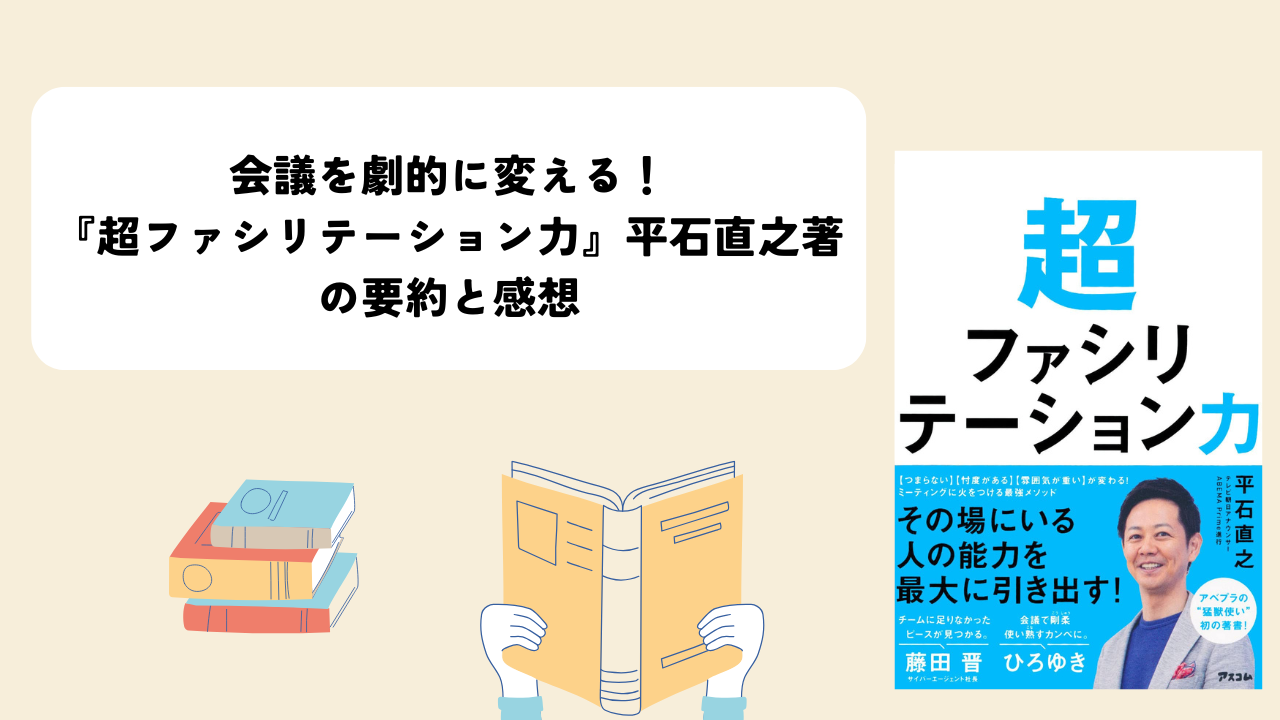



コメント